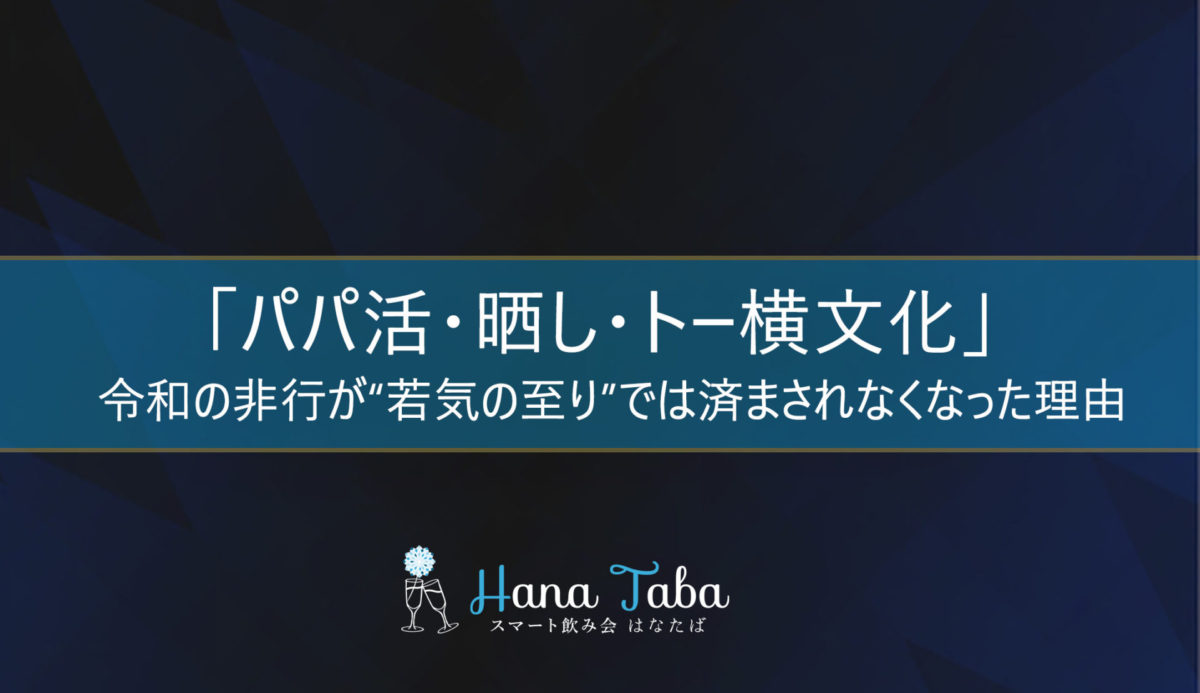
皆様こんにちは、夜のひととき です。
援助交際、薬物、自傷、芸能人の不祥事。
どれも目新しいものではない。昭和にも平成にも、こうした“逸脱”は常に存在してきた。
だが、令和のいま、こうした出来事がもたらす印象は、どこか根本的に違っている。
似たような行為が繰り返されているはずなのに、そこには明らかに“質の異なる闇”がある。
それは、行動そのものではなく、それを取り巻く社会の変化――
孤立、無関心、無責任、そして、極端に歪んだ価値観によってもたらされたものだ。
見られることが前提になった自己破壊
今、SNSを開けば、パパ活の募集投稿やトー横に集まる子たちの記録、自傷アカウントの切実な投稿がいくらでも流れてくる。
その多くは、「助けてほしい」という言葉を直接使わず、「見てほしい」「気にかけてほしい」というかたちで存在している。
だが、そこに返ってくるのは、真っ当な関心ではない。
興味本位の“観察”、炎上を期待する“晒し”、もしくは、何も届かない“既読スルー”だ。
人に見られたいが、救われたいわけではない。
その矛盾が、現代の非行をより苦しく、残酷なものにしている。
昔の非行には「責任」があった
かつてのヤンキー文化や不良行為にも加虐性はあった。
暴力や差別的なふるまい、排他性も確かに存在していた。
だが、そこには「責任」があった。
自分の顔と名前で、人としてぶつかっていた。
仲間と群れるには上下関係があり、ルールがあり、ケジメを求められた。
家庭や学校、地域社会には“叱る大人”がいた。
間違ったことをすれば怒られ、時に補導され、謝罪や償いが必要だった。
今はどうだろうか。
SNS上で誰かを晒し、追い詰め、拡散しても、そのほとんどは匿名のまま。
手軽に加害ができて、責任は取らなくていい世界――
それが、令和の日本で当たり前になっている。
世界を“心地よさだけ”で塗りつぶす時代
さらに厄介なのは、SNSによって自分にとって不快な情報や意見を簡単に排除できてしまうということだ。
ブロック、ミュート、フィルター。
自分に合う言葉、自分に優しい人間、自分と似た価値観だけに囲まれて生きていける。
これは一見、ストレスの少ない良い環境に見えるかもしれない。
だが、聞きたくないことを聞かずに済む世界では、“聞くべきこと”すら届かなくなる。
異なる立場の声、耳の痛い忠告、不器用なやさしさ――
そうしたものをすべてシャットアウトした先に残るのは、
“違うものを認められない自分”であり、
“他人を攻撃しても平気な心”だ。
価値観が歪むとは、何かに染まることではない。
異なるものを受け入れる余白を、自分で失っていくことなのだ。
“触れること”でしか得られない自尊心と想像力
こうした閉じた社会の中で、改めて思う。
人間にとって、本当に必要なのは「関わること」ではないだろうか。
たとえば、野良猫に餌をあげるとき、そこに生まれるのはほんの小さな責任と誇りだ。
野良猫に餌をやるというたった一つの行為で、
「誰かを満たした」という小さな誇りが自分の中に芽生える。
その一方で、この場で餌をあげたことにより野良猫は何度もここに来るようになる。
近所の住民は野良猫が来ることで被害を受け、迷惑するかもしれない。
これはあなたが猫に餌をあげたことによる小さな責任だ。
その関わりには誰の評価もないが、“自分が誰かのために何かをした”という確かな実感と責任がある。
誰にも迷惑をかけずに生きようとすれば、
誰からも必要とされずに生きることになる。
植物を育てることも同じだ。
水をやり、日光の向きを気にし、虫を取ってやる。
花が咲いたとき、その喜びは“結果”以上に“過程”がくれたものだと気づく。
世話をしなければ枯れ、エサをやらなければ死んでしまう。
そうした実体験は、「自分の選択と行動には影響力がある」という感覚を自然に育ててくれていた。
今、そういった小さな“責任”を経験する機会が急激に減っている。
ボタン一つで買い物ができて、通知一つで他人とつながれた気になれる社会では、
「自分が誰かのために何かをしている」という実感が、ほとんど育たない。
観葉植物を水やりしながら元気かどうかを気にする、
台風のあと、ベランダのプランターが無事かを確認する、
そういった些細な気づかいの積み重ねが、実は“人に対するやさしさ”や“自己肯定感”と強く結びついている。
生き物を育てるということは、同時に「生きることへの想像力」を育てるということなのだ。
人と触れ合う、動物と関わる、植物を育てる――
そうした“手間”の中でしか、人は本当の意味で自尊心や想像力を育てることができない。
その行動に、誰かが「意味がある」と決める必要はない。
自分の手で確かに関わったという感覚こそが、今の時代に失われつつある“生きている感触”なのだ。
他人の人生もまた、知ろうとしなければ見えないものばかりだ。
猫がなぜ夕方に現れるのか、
あの子がなぜ学校をやめたのか――
触れて、知って、想像する。
そのプロセスが、暴力や無関心を防ぐ唯一の予防線なのだと思う。
知ることでしか得られない“他人の人生”がある
誰かを晒して、笑って、終わらせる。
それが今のSNSにある無数のやりとりだ。
けれど、そこにあるのは一瞬の情報であって、“人間の物語”ではない。
一輪の花が咲くまでの土の話、
猫がなぜこの時間に現れるかという習性、
炎上していたバイトの子が、実は親の介護をしていた話――
知るということは、情報ではなく“背景に触れること”。
それができた瞬間、人は加害者になれなくなる。
むしろ、なぜそのようなことをしているのかと、立ち止まるようになる。
SNSでは、無数の“部分的な事実”だけが切り取られて流れていく。
でも、誰かの人生を少しでも深く知った経験がある人は、その流れに完全に乗ることができない。
それは、“自分が何かを知った重み”を、自分の中に感じているからだ。
終わりに
令和の非行が救いようのない闇に見えるのは、
その行動のひとつひとつが危険だからではない。
それに対して何も言わない現実社会、誰も関わらない世界、誰かに委ねるばかりの空気があるからだ。
効率化された社会のなかで、非効率なやさしさを選ぶこと。
それが、令和という冷たい時代に対する、最大の抵抗なのかもしれない。
人に触れる。
生き物と関わる。
“無駄”で“手間”で“うるさい”関係を、自分の意志で持つこと。
それが、整いすぎた社会に人間らしさを取り戻す一歩なのだと思う。
情報に囲まれたこの時代にこそ、
触れなければ得られない温度と、責任のあるやさしさを、もう一度大切にしていきたい。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。


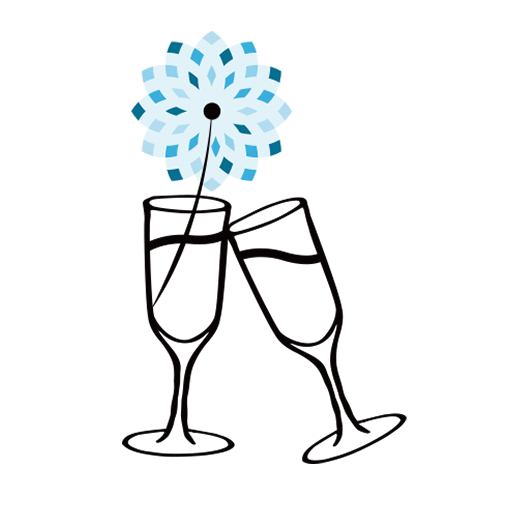










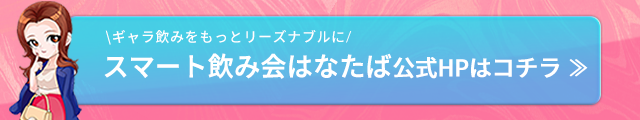
この記事へのコメントはありません。